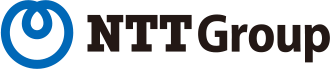『教えてヒロさん!』~自律分散システムはWeb APIから~
投稿者:藤野裕司

従来のITの世界では、新システムを作ろうとすると、既にある機能のうち必要となる機能とそれに加えて新しい機能を作りこまなくてはなりませんでした。既に必要な機能があったとしても、それを捨てて最初からシステムを作り直す必要がありました。
しかし、自律分散型のシステムでは、既存の機能と追加の機能を相互につなぎ、新旧のシステムを自在に連携して柔軟に利用しやすく組み立てることを考えます。
そのためには、システムをいちから作るより、採用可能なものを柔軟に取り入れ、不要となったものは適宜取り払う。つまり、いいとこ取りをしたシンプルなシステムを目指すのが、この時代に相応しい自律分散型のシステムとなるのではないでしょうか。
これを実現する手段として、Web APIが今注目されています。
産業システムでWeb APIを活用する方法とその理由を考えてみましょう。
● Web APIとは
まず、Web APIとはどのようなものかを考えてみます。
Web APIとは、プログラム同士が(httpもしくはhttpsを介して)直接会話する方式で、Web上に提供されているプログラムを利用することができる仕組みのことです。ユーザがWebブラウザから操作しなくても、一連の流れを実行することができます。

● Web APIが活躍する場面
Web APIの仕組みについて、より掘り下げた説明としては次の通りになります。業務やサービスを提供するWebサーバに、クライアントからアクセスを受けることができる窓口を開けておき、Webクライアントが決められた形式でWebサーバにアクセスします。
サーバはアクセス仕様に従って処理を実行し、結果をWebクライアントに返します。
その流れを具体的に考えてみましょう
( 1 )PCから業務サーバにアクセスする処理の流れ
従来なら手操作で業務サーバのプログラム操作をするところを、PCからWeb APIクライアントで業務サーバにアクセスし、プログラム同士の処理で業務を実行する。
具体例:PCのアプリケーションに経費情報を入力し、業務サーバにデータを登録

( 2 )サーバ同士の連携処理の流れ
異なるサーバ群が、連携しながらひとつの処理を行うような流れを作ることができる。
サーバ業務Aがクライアントとしてサーバ業務Bにリクエストを出し、それを受けたサーバ業務Bが処理を行う。処理結果が出たら、今度はサーバ業務Bがクライアントとなりサーバ業務Aにリクエストを出し処理を引き継ぐ。
それを交互に行えば、両業務が継続した流れで処理を続けることができる。
具体例:人事システムからSE稼働情報を抜き出し、会計システムに連携する

( 3 )サーバ業務から各種サービスにアクセスし複数クラウドのデータを集約
自社業務からWeb APIを公開している各種サービスクラウドにアクセスし、データの授受を行う。集めたデータを自社業務で集約し、あたかもひとつの業務のように処理を継続できる。
具体例:自社の経費業務サーバから交通費精算クラウドにアクセスし、経費の処理を行う

● Web API市場は拡大している
このWebAPIは、本当に有望な機能で、すでにAPIの市場は急拡大しているようです。
API管理市場は2022年から2030年までに年平均成長率(CAGR)は34%で成長し、最終的に316億米ドル(4兆7000億円)に達すると言われています。
日本のレポートでは、古いデータになりますが、日本能率協会研究所が2019年発表の資料で「2024年に880億円になる」との予測がありました。

【URL】http://search01.jmar.co.jp/mdbds/
より詳細なデータは、どれも有料になるので入手できませんでした。(^^ゞ
ご存じの方があれば教えていただけると嬉しいです。
● 市場が拡大する理由
一般的には、オープンな環境で利用できるメリットが大きな特徴としてあげられています。「メインフレームで使われるような独自OS」や「固定電話で利用される限定的な通信プロトコル」でないところが、最大の強みとなるようです。
- プラットフォームに依存しない
- LANやインターネット経由で接続
- クラウドやモバイルとの親和性が高い
- グローバル展開が可能
- オープンソースが豊富で拡張性が高い
- 誰でも簡単にプログラムを作ることができ、簡単に使える
● 企業間データ連携としてのWeb APIの強み
特に近年は、どのような使い方ができるか、Web API 特有の強みはなにか、などが企業間で注目されています。
またWeb APIは、企業間におけるデータ連携の手段として盛んに導入されているEDI(Electronic Data Interchange)とも違いがあります。
そこを掘り下げてみましょう。
( 1 )前提となる設備が不要
EDIは、最低限エンジンとなるEDIツールの利用が必須であるが、Web APIはコンパクトなコマンドレベルのクライアントからの利用が可能。
EDIは、EDIツールを含んだEDIシステムとしての構成が前提となるが、Web APIはシステム利用も独自プログラムでの利用も両方の同時利用も可能である。
( 2 )難しい理屈は不要
EDIは、通信プロトコル、シンタックスルール、業界ごとのEDI標準の理解と標準を遵守する仕組みが必要だが、Web APIは接続方法を理解するとどのような相手ともつなぐことができる。あとは接続先との業務フローや項目等の意味を理解するだけでよい。
とはいえ、すでにEDI標準が利用されている場面では、標準の遵守が重要。
( 3 )リアルタイムで接続
EDIはファイル単位のバッチ運用が前提となるが、Web APIはバッチ運用もリアルタイム運用もその両方の同時運用も可能。
( 4 )社内・企業間・クラウドがシームレス連携
企業間はEDI、社内はファイル転送・EAI・ETLと別システムとなっている場合が多い。一方、Web APIでは、企業間・企業内・クラウドサービス、国内・海外がすべてシームレスでの接続が可能。
( 5 )Web APIで多くのデータや機能が公開されている
世の中には、すでに企業で利用できる有益な「データや機能」がサービスとして多数公開されており、Web APIを活用するとそれらを簡単に利用できる。
( 6 )Web APIも通信プロトコルとアプリケーションデータを分けて考えることができる
Web APIは、ひとことで「つながる」といっても、具体的にどのようにつながるのかわかりにくい。そこで、通信プロトコルとアプリケーションデータに分かれる、と考えるとよいかもしれない。EDIに例えるなら、「目的に応じた通信プロトコル」と「EDI標準や業務に応じたアプリケーションデータ」に分けて考えるように、Web APIでも通信関連の設定とアプリケーションデータに関連する設定に分けて考えることができる。
設定内容は、国際標準で定められているので、そのルールに従っていれば、どのようなパターンでもつなぐことは可能である。ただ、なんでもむやみに設定すればよいわけではないので、そこを十分に理解できていれば自分で開発・設定してもよいし、難しいと考えるなら、信頼できるツールやサービスを利用するのもおすすめである。
● オープン系ならWeb APIで比較的容易にシステム間をつなぐことができる
このように急拡大するWeb APIを活用すると、EDIと同様の企業間連携も、EAIやファイル転送などの社内連携も、そしてクラウドとの連携も、同じ仕組みでつなぐことができるようになります。
これこそ、求める機能やデータを自在に活用する方法。つまり、自律分散システムを比較的容易に構築できるこれからの方法といえるのではないでしょうか。
しかし、このようなメリットばかりに気を取られてはいけません。
なにごとにも、メリットがあればデメリットもあります。
そのあたりについては、後の章で課題や配慮点・注意点について詳しく説明しましょう。
今回は、Web APIとはどういうもので、市場は拡大しつつあることや、企業間連携の仕組みとして見たWeb APIの強みなどを考えてみました。
次回は、現状の産業システムを振り返りながら、Web APIを使いこなす方法を考えてみたいと思います。