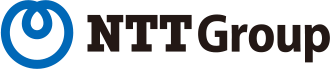『教えてヒロさん!』~個別システムがつながりデータインテグレーションが実現できる~
投稿者:藤野裕司

今回は、「データインテグレーション」とはどのようなものかを考えてみたいと思います。
これまでは、社内システムや企業間のデータ連携は各々別の形で行われていました。
従来のバッチ業務で行われているファイル単位のデータ交換は、現在の業務においても重要です。
今はクラウドやサービス間の連携も視野に入れなくてはならないのです。
また、世の中に埋もれている貴重で有益なデータを十分に活用できていないのも事実です。
「高速大容量同時多接続」のインターネット時代に、従来の方法のままでよいはずはありません。
● データ連携基盤の構築
また、個々のシステムを見てみると、業務内容、データの変換、データの管理機能、通信機能などを個別に持っていました。
この中で業務固有の内容を除き、他の機能は共通化できるのではないでしょうか。
共通化できる機能を集約したものは「データ連携基盤」と呼ぶことができます。
各企業がこのデータ連携基盤を自社で運用できれば、企業独自のデータ連携システムの構築が可能となり、コスト削減や運用の高度化、サプライチェーンの精度向上を実現できるのです。
これで企業内データインテグレーションは出来上がります。

● データインテグレーションサービスの活用
しかし、これを実際に実現するにはかなり充実した技術力や運用体制が必要となります。
そのようなノウハウ・体力に不安な場合や、自社の本業に力を集中したい場合には、どうしたらよいのでしょう。
その場合、これらすべてを任せられる安全安心な環境があればいうことはありません。
NI+Cには、データ連携基盤に加えて、運用管理やヘルプデスクなど、専門的なサ-ビス環境があります。
面倒なことはお任せください。
データインテグレーションサービスとして、これらすべてをまとめて提供いたします。
( 日本情報通信EDI関連サービス )

最近は、やはりWeb APIによるデータ連携のご要望を多くいただいております。
Web APIを活用すると、ファイル単位のデータ交換も、項目やレコード単位のトランザクション連携も、アプリケーションに対応した問い合わせ応答型のコミュニケーションも、比較的自在に対応できるからです。
とはいえ、前回ご説明したように、結構注意点が多いのも事実です。
そこは何とか克服していきたいものですよね。
そういうところこそ、専門サービス、つまり「データ連携プラットフォーム」サービスに任せるのがいいのではないでしょうか。

● 自律分散型社会へ
サービスを利用することによって、最小限の自社環境で、最大限の外部環境を活用する。
プラットフォームサービスは、まさにこのようなことを実現するものと言えます。
このように、自社内の共通機能を統合してデータ連携基盤を構築したり、データ連携プラットフォームサービスを活用してデータインテグレーションを実現したりすることが可能になります。
これからは、広く散在する価値あるデータや、あちこちで提供されている有効な機能をつなぎ合わせて、自律分散の世界に進んでいくのだと思います。
今回は、データインテグレーションとはどのようなものかを考えてみました。
次回は、自社のみならず様々な企業やサービスが相互に連携し、社会全体が一つにつながりあう「エコシステム経済圏」が実現できる世界を考えてみようと思います。