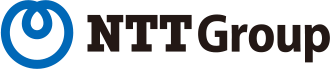NI+C EDIシリーズ<第3弾>
EDIテクノロジーの変遷
投稿者:國藤

みなさん、初めまして
NI+C バリューオペレーション本部EDIサービス部の國藤です。
日本情報通信のEDIパッケージである、EDIPACKの開発を担当しています。
今回はEDI通信の技術的な側面について、その変遷を見ていこうと思います。
黎明期
EDIの誕生は1970年代とされています。
が、その当時は業界標準がなく、通信相手ごとに手作りするものであったようです。
技術的にもそれぞれ異なる通信方法を使っていたと思われます。
とはいえ、当時のことは話に伝え聞いたのみで、想像するしかありませんが。
国内においてEDIの標準化が進むのは1980年代に入ってからで、JCA手順、全銀協手順が策定されます。
どちらも通信方法としてはBSC伝送制御手順を利用しており、制御文字を使ってデータの始まり、終わりなどを示し通信を行います。
インターネット化
1997年になると全銀協手順をTCP/IPに対応させた 全銀TCP/IP手順が制定されます。
また、WEB-EDIが出てきたのもこのころで、インターネット回線があればブラウザベースでデータのやり取りができるようになりました。
2000年前後には企業内のクライアント/サーバシステムがWEBシステムに置き換えられていたことを考えると、WEB-EDIはその先駆けとなる動きではなか
ったでしょうか。
流通BMS
2007年に流通BMSが制定されます。
流通BMSは以下の3つのプロトコルからなります。

注目すべきはどれもHTTP上に構築された仕組みだという点です。
つまりHTTP Clientを用いて相手にPOST するプログラムが必要という点です。
WEB Service(今日でいう、WEB上で使えるサービスという意味ではなく、技術仕様としてのWEB Service)が提唱されたのが2000年代前半なので、数年の差はありますが、時流に沿った展開ではないかと思います。
また、通信方法としても、データフォーマットとしてもXMLが活用されていますが、これも当時は最新とはいかないものの、普及している最中の技術だったように思います。
JXのメッセージ構造

まとめ
近年ではREST APIを使った連携も増えてきています。
EDIPACKではWebScriptという独自プロトコルを追加することで、プログラミングレスで通信相手のREST APIに対応することができます。

今回はEDIの歴史を追いながら、利用されている技術を概観してみました。
EDIというと、どこかレガシーなイメージを持たれるかもしれませんが、このように歴史を見ていくと、その時その時の技術を取り込んでいっていることがわかります。
それではまた次回EDIサービス部の記事をお楽しみにしていて下さい。