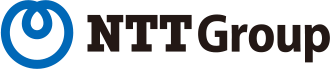NI+C EDIシリーズ<第11弾> "簡単に始められるEDIを扱う際の落とし穴"
投稿者:福田

皆さん、こんにちは
日本情報通信 バリューオペレーション本部 EDIサービス部の福田です。
今回は簡単に導入可能なSFTPやWeb-EDIを使ったEDIについてのメリット・デメリットや
今後について取り上げたいと思います。
まずは、導入が容易なEDI手順のメリットについてご紹介していきます。
1.導入が容易なEDI手順のメリット
全銀・JCA手順などのEDI手順はアナログ/ISDN回線といった一般の通信回線や専用線/VPNを取引先ごとに用意する必要があり、手順ごとに専用ソフトウェアを購入しコンピュータへインストールして使います。
この方法では通信コストがかかり、また取引先ごとにソフトウェアを使い分ける必要があったため、
取引に伴う処理が煩雑なものになっていました。
一方でSFTPやWEB-EDIはウェブ上にシステム構築を行うので、ユーザはOSに標準でインストールされているソフトウェアやウェブブラウザを通じてデータの送受信やシステム操作して商取引を行います。
さらにSFTP/WEB-EDIのメリットをそれぞれ紹介します。
SFTPのメリット
・FTPに関しては、専用線やVPNなどのセキュリティ上の問題を解決すれば比較的簡単に導入でき
る。
・FTP/SFTPともにWindowsやLinuxに標準搭載されているものであるため、PC購入をすれば導入が
可能な状態になる。
・コマンド操作のため自動化も容易にできる。
Web-EDIのメリット
・企業間の商取引に必要なビジネス文書のやり取りを自動化できるため、請求書などのペーパーレス
化が可能。
・クラウドで提供されているソリューションであるため、専用システムを構築する必要がなく低コス
トでの導入が実現できる。
・従来の電話回線を利用したデータのやり取りよりも、最新の通信回線を利用したデータのやり取り
の速さは数段アップしており、従来のEDIよりも通信速度が高速である。
・暗号化技術の発達により、現在のインターネット回線は非常にセキュアなものが多い。
企業間の商取引業務もセキュアな回線を利用して行われるため、従来のEDIと比べてもセキュリティ
対策は万全だといえる。
※従来のEDIは専用回線を使用しており、周りと連携ができないものであったが、専用回線のほうが
優れているとは限らない。
2.導入が容易なEDI手順のデメリット
取引先企業とのEDIシステムの仕様が異なるものである場合、商取引の電子化を行うことはできません。そのため 企業ごとにEDIシステムの仕様がどのようなものであるか確認する必要があります。

しかし、SFTPやWEB-EDIはEDI手順としては標準化されておらず、企業独自のデータ交換仕様が存在しています。
例えばSFTPでは企業ごとにディレクトリ構成・ファイル命名仕様が異なり、またデータ通信完了のフラグとして以下のような仕様が複数存在しています。
・転送中のEDIデータに一時的に別ファイル名を付けておき、転送完了後に本来のファイル名に変更す
る。
・転送中のEDIデータを一時的に別ディレクトリに転送し、転送完了後に本来のディレクトリに移動さ
せる。
・転送後のEDIデータに、別ファイルをサイズゼロで作成して、それを完了フラグとして扱う。
これらの組み合わせで仕様が多く存在します。
上記で上げた例は送信時の例ですが、受信側でもこのような仕様が多く存在します。
SFTPやWEB-EDIを用意する企業(主に発注企業)はEDIの一本化が達成できているが、受注企業は取引先の用意するWEB-EDIの種類だけ接続先や操作手順、オペレータを常に管理しなければならなくなります。
また自動化するためにWEB操作自動化システムを構築しても取引先のWEB-EDI画面仕様が変わってしまったとすると、WEBブラウザの仕様変更により常に変更・保守作業を強いられてしまいます。
FTP/SFTPに関しては自動化は容易ですが、企業独自のデータ交換仕様が設定可能なため、受注企業は取引先ごとに異なる仕様を満たす対応が必要となってします。
したがって受注企業側がEDIの恩恵を受けられなくなってしまいます。
NI+C EDIシリーズ<第6弾>で紹介していた伝送フォーマットがばらばらな状態と同じような状態になってしまいます。

3.EDI業界の流れ
EDIの2024年問題の電話回線やISDNがサービス終了に備えて、これらを使用していたレガシー系といわれているEDIから次世代系といわれるインターネット系のEDIに移行する動きが非常に活発になっています。
さらに、SFTPやWeb-EDIは専用ソフトをインストールする必要がないため、PCとインターネット回線があればすぐにEDIによる取引が開始できます。
したがって、非常に低コストでEDIを導入することが可能です。
しかし、前項でも述べた通り人手による操作を必要とするWeb-EDIや企業ごとに独自のデータ交換仕様が設定可能なSFTPは、”企業間で電子データを自動処理によって交換する”というEDI化の根幹ともいうべき要素が、受注企業側において完全に抜け落ちています。
4.良くするためには
発注企業は受注企業が導入しやすいSFTPやWEB-EDIを用意するのは良いですが、自動化が容易な標準化されたEDI手順の受け口も用意するべきであると考えます。
例を挙げると、
ebMSv2/JX/AS2/全銀協標準通信プロトコル(TCP/IP手順・広域IP網)等
NI+C製品のEDIゲートウェイサービスでは上記の4手順に対応しております。

5.おわりに
今回、Web-EDIについてお届けしましたがいかがだったでしょうか。
SFTPやWeb-EDIにはメリットも多くありますが、デメリットについても多くあることが理解いただけたと思います。
EDIに関するご相談がございましたら、以下からお願いいたします。
それでは、また次回EDIサービス部の記事をご期待ください。